街に根ざし、もの・こと・ひとの出会いを仕掛けるひと – 藤崎百貨店 千葉伸也さん –

朝8時。青葉区一番町にある藤崎百貨店の物流館では、トラックや荷台を押す人々が絶え間なく出入りしている。そのすぐ横の従業員通用口から、スーツの男性が笑顔で現れた。藤崎百貨店に勤める千葉伸也さんである。
「朝の時間帯は、地下の食品売り場の商品が続々と届いています。大きな催事の時は、出店事業者様と一緒に従業員が荷物を運ぶ手伝いをするんですよ。」行き交う人に挨拶をしながら、スマートな身のこなしで従業員用エレベーターに案内してくださった。
開店前のまだあかりの消えた館内に降り立った瞬間、香水や衣料品の匂いが鼻をかすめる。百貨店の匂いである。フロアを横切り、千葉さんのお話を伺うために、本館3階の「ケヤキカフェ」に向かった。
大きな窓から青葉通が望める解放感のある空間には、広々とした小上がりスペースがあり、2015年にオープンして以来、赤ちゃんや小さな子どもを連れた若い子育て層で賑わっている。
開店前の静かな店内で朝の青葉通を眺める千葉さんは、コンテンツデザイン部でMD(マーチャンダイジング)計画を担当されている。千葉さん曰く、「藤崎ならではのコンテンツを作り、お客様にお伝えし、共感をいただく」仕事だという。入社から19年間、藤崎ならではのコンテンツづくりをどのように経験されてきたのだろうか。
まずは、一日のスケジュールと、百貨店で働くことを目指した経緯を伺う。
百貨店の仕事とは

− 千葉さんは普段、どんなスケジュールで働いていらっしゃるのでしょうか。
朝9時半頃に出社し、まずは開店前の店頭のチェックから始めます。 毎週売り場の内容の切り替えがあるので、お客様と同じ様にエスカレーターに乗って、そこからPOPがちゃんと見えているか確認したり、マネキンや看板の位置を直したりします。藤崎独自のコンテンツをお披露目の際には、朝礼で、売り場に立つ販売員の皆様に企画の意図を説明したりもします。
午前10時の開店後は、企画会議や私がまとめているチームとのミーティングを行います。チームに総勢17人が集まっていて、今後のスケジュールを確認しながら様々な計画を詰めていきます。
− どんなことをされているチームなのでしょうか。
商品を買い付けてくるバイヤーや、商品を開発したり販売戦略を考えたりするマーチャンダイザーと呼ばれる人が集まるチームです。バイヤーによって、それぞれに専門分野があり、例えば、お酒のスペシャリストがお酒の別注を作っているということで状況を尋ねると「作付け前の田んぼの土地をおさえてきました」なんて返事がきたりするので、商品を買うだけにとどまらない仕事です。三越伊勢丹様のような大規模の百貨店には、スペシャリストが100人単位でいらっしゃると思いますが、地方百貨店の規模でいうと、我々は専門性の高い人材が比較的多い方だと思います。
午後は、商談に行ったり、百貨店業界以外の方々と進めている企画の打ち合わせをしたりと、社外に出ていることも多いですね。社内に戻ってからは閉店後のチェックなどを経て、催事などの準備で忙しくない時は、大体夕方6時から夜7時半頃に退勤という感じです。
− お仕事の後は、どの様に過ごされていますか?例えば、飲みに行かれたりもされますか?
もちろん、社外の色々な方と飲みに行きますよ。お客様に向けてコンテンツを作っていますので、今どんなものが流行ってるのかとか、どういうものが街に溢れているのかは、積極的に動いて見聞きしに行っている感じですね。百貨店の中だけにいると中のことだけになってしまいますので。
地域のカルチャーを追う学生時代

− 仙台ご出身の千葉さんですが、どんな学生時代を過ごしていましたか。
流行のカルチャーを追っていた学生時代でした。通っていた仙台三高は私服校だったので、放課後は街に繰り出し、レコード店や古着屋を巡っていました。「コムデギャルソン」などのドメスティックブランドにも興味津々でしたが、高校生のバイト代はたかが知れていますので、お店で店員さんとお話しして回るだけ。それでも刺激的な日々でした。
そんななかで興味を持ったDJの活動では、学校外の同世代の仲間が沢山できました。皆でターンテーブルを買って、街中のスタジオを借りて仲間を集めてパーティーやイベントをしたり、学園祭で企画をやったりしていました。1990年代の仙台のカルチャーを仲間と一緒に体験したことは今でも大きな財産になっていますし、その時の仲間は今も色々なところで活躍していて刺激を受けています。そんな訳で勉強は後回しにしていたのですが、最後の年は一念発起して仲間と勉強に励み、明治大学の政治経済学部に進学しました。
− 大学では、どんなことを学んでいましたか。
地域のスポーツやご当地キャラクターといったローカルコンテンツを通じたマーケティング、行動経済学を専攻していました。勉強していくなかで、カルチャーの力や、今でいう推しの力ってすごいなと改めて思ったわけです。特に、2002年日韓ワールドカップの時の人を動かす熱量を肌で感じた時に、ローカルでこれを再現できたら面白いだろうなと思ったんです。
− それが、地元・仙台での就職を考えることに繋がったのでしょうか。
それもありますね。様々な業種の採用試験を受けるなかで、百貨店って面白いかもしれないと感じるようになっていました。元々ファッションが好きだったので、目まぐるしく変わっていく時流の風をど真ん中で浴びていたかったですし、土着のカルチャーに魅力を感じていたこともあって、地元の百貨店もいいなと。藤崎百貨店は調べてみると歴史があり、うちの両親も「藤崎さん」と呼んでいて信頼もあるのかなと思い入社しました。それが、2005年のことです。採用面接の時に高校時代の仲間とばったり会い、入社して同期になったなんてこともありました。
藤崎百貨店のあゆみ

藤崎百貨店のあゆみは、1819年に初代・藤﨑三郎助氏が呉服業を営む「得可主屋(エビスヤ)」から始まった。今も使われている商標は、福徳円満・和心協力の意を込めた赤丸に、エビスヤの「エ」と「一番をもって貫く」の意を込めた「一」が描かれている。
1891年、4代目・三郎助氏により、本業の呉服店に加えて経営の幅を拡げ、1900年初頭には、ブラジル・サンパウロへの出店や、インドや台湾との貿易などを精力的に展開した。
取り扱う商品を大幅に増やして陳列する今の百貨店スタイルを確立したのが、1919年。この時、お客様向けの呼び名を「藤崎マーケット」としていた。
1930年、現社名の「株式会社藤崎」へ。1932年にルネッサンス風建築の新館をオープンさせた。現在は、青葉通に面した藤崎本館、ぶらんどーむ一番町にある藤崎一番町館と藤崎大町館、東二番丁通りに面したファストタワー館の4つの店舗に加え、宮城県内と東北各地に地域店舗を展開している。
千葉さんが入社した2005年は、泉区・寺岡に百貨店らしい上質な商品を扱うスーパーマーケット型店舗を出店した年。2011年の東日本大震災を経て、地域の繋がりの場である地域店舗はますます需要を高めていく。2019年には創業200年を迎え、百貨店の中に居ながら、その歴史の重みと時代の変遷を肌で感じてきたに違いない。
ここからは、千葉さんのお仕事と地域の関わりを具体的に伺っていく。
百貨店のマナー

− 千葉さんに初めてお会いした時から、所作がスマートだなぁと感じていました。百貨店の作法やマナーなどはあるのでしょうか。
入社当時、上司の監督の下でひたすら歩く研修というのがありまして、そこで身のこなしは勉強になりました。マナーでいうと、例えばお辞儀。お客様が通られた時は15度、お見送りの時は30度、手の位置は利き手がすぐ出るように上にするなど、さまざまなルールがあります。
−接客や言葉遣いなどは、従業員の方やお客様と日々関わる中で身につけていくものなのでしょうか。
そうですね。百貨店というのは、本当に多様な人が集まっています。八百屋さんから職人さんまで様々な職種の方が出入りしていますし、約1,700人の登録のうち常時1,000人近くが館の中で働いています。お客様のためにというところは皆同じですが、さまざまな立場の方々が集まっているので、それぞれの目標や思いがあるわけです。我々がこうしてほしいという要望は伝えますが、向こうの意図があったりもしますので、そこは会話をしながら丁寧にすり合わせていく。そういうことが最終的にはお客様にも伝わります。
お箸と婦人服、それぞれの提案

− 入社して初めてのお仕事について教えてください。
はじめに配属されたのが、大町館2階にある食器売場で、任されたのは「お箸」でした。百貨店というと婦人服のイメージが強かったので、当初はお箸というアイテムに今ひとつイメージが湧いていませんでした。しかし、実際に担当してみて、食器やお箸は贈り物の需要が高く、百貨店はギフトの面もあるんだなということが実感としてわかってきて、面白くなってきました。当時は、引き出物を包んだり、のしやリボンをかける作業を黙々とやっていました。
− 美しい包装は、百貨店でものを買う醍醐味のひとつですよね。
包装に関しては、売り場のお姉様方に仕込んでいただきました。リボンの結び方一つ取っても、最後にキュッと締めないとへたってきてしまいます。包装も力を入れると綺麗にできるのですが、入れすぎると包装紙が破れてしまう。その塩梅が難しいところはありますね。
食器売り場を二年間経験し、売り上げを管理するPOSシステム構築を一年間経験した後、婦人服売り場へ異動しました。
- お箸からお洋服へ、それぞれの提案の仕方はどのように違いますか。
お箸は、素材、形、産地などそれぞれの切り口で編集し、そこにストーリーを見出して提案していました。お洋服の場合、商品自体の機能や魅力の提案も大切ですが、お客様との会話からその方の普段のワードローブを想像し、使うシーンを提案していくのが違うところですね。また、お洋服は春夏秋冬のシーズンごとにお客様とコミュニケーションを取っていくことが非常に大事なので、お買い上げいただいたお客様に新作ご案内などのお手紙を出したりしていました。
婦人服売り場で経験を積んだ後、株式会社三越伊勢丹様に出向することになりました。

アパレル商品づくりのプロセス

− 三越伊勢丹では、どのようなことをされていたのでしょうか。
当時、三越伊勢丹様が独自で編集しているショップが全国に23店舗あり、その店舗が藤崎にも入っていました。そのマーチャンダイザーとして、商品作りから店長向けの展示会の実施、商品の納品から売り上げのチェックなどの一式を担っていました。
− お洋服を売るだけではなく、作るところから担当されるとは、アパレルメーカーのようなお仕事ですね。
そうですね。この経験は本当に大きかったです。お客様のニーズに合った商品を作るため、膨大なデータから合う生地を探したり、生地屋さんやパタンナー、工場とやりとりをし、生産して販売するまでの、ものづくりを通して一連の流れを見せていただきました。
三越伊勢丹様は大企業ですし、仙台では素敵なライバルの仙台三越様の親会社でもあります。我々も情熱を持ってやっていましたが、大企業の仕事の仕方や企画に対する熱量に圧倒されましたし、失敗しながらも学ぶことが多かったですね。この時期に、全国各地に仲間ができました。
− アパレル商品は、実際は春夏でも、秋冬のアイテムを進めたり、シーズンを前倒して作りますよね。お客様からのニーズを拾うタイミングが難しいと思うのですが、どんなことに気をつけていますか。
アパレルのものづくりはかかる期間が長いので、作っている間に世の中の状況やお客様のニーズが変わってしまうことも多々あります。実際に、2023年は暖冬にも関わらず、店頭にはダウンジャケットが多く並んでいました。しかし、私の上司の言葉を借りれば、「百貨店は変化対応業」。マーケットとお客様の気持ちの変化を、我々がどう聞き取り、お客様の欲しいものを欲しい空間で提案できるか。それを常に念頭に置くようにしています。
お客様のニーズは、世の中の状況だけではなく地域性も大きいことを、三越伊勢丹様への出向後、東北及び宮城県各地の新しい地域店舗の開発を担当するなかで実感していきました。
地域の魅力を汲み、外に伝える

− 一番町にある藤崎本店(4館)と地域店舗との違いはどんなところでしょうか。
当時、地域店舗では主にギフト用の商品を扱っていましたが、これからはギフトだけではなくて、生活用品を含めたライフスタイルの提案をしていくということで、本店と連動したブランドの誘致や、行政や学校との連携を想定したイベントスペースなどを有した4つの新店舗の品揃えや機能をチームで考案しました。
藤崎本店は、平均一年に1〜2回、各シーズンに一回程度お越しいただく方が多いのに対し、地域店舗は、週1〜2回も足を運んでくださる方々がいらっしゃいます。飽きがこないよう、そこでの会話が弾むように商品の陳列を工夫し、各店舗のオリジナル商品開発にも取り組みました。地域店舗は、海沿いから山の方まで様々なエリアにあるので、改めて地域性や地域の魅力に触れて、面白さを実感できましたね。
2018年、長期視点でマーケットを捉えて新たな事業の種を実験・実証していく部署として、「未来創造ラボ」が新設され、その一員となりました。
そこでは、仙台市と協働し、地域ブランド「都の杜・仙台」を手がけました。ブランドのネーミングは、仙台のキャッチフレーズとして浸透している「杜の都」ではなく、「都の杜」。これは、色々な機能が集まった仙台を俯瞰して見ると森に見えるというのが由来です。このブランドでは、外から仕入れたものを地元の人に販売するというよりは、地元のものを集め、色々な方とタッグを組んで、それを外に伝えていくという県外向けのプラットフォームを目指していました。
− これまでも沢山の商品開発を手がけていらっしゃるなかで、「都の杜 仙台」の名前を掲げた時、意識されたことやこだわったところはどんなところですか?
我々のアイデンティティや新しい象徴、 強みを作るところを念頭に置いていました。我々は、商品のブランディング、物流やレジなど色々な機能を自社で持っているので、仙台市と参画してくださっている100社を超える事業者さんと一緒に団体戦でやることでプラットフォームとしてお役に立てるのかもしれないと考えました。オンラインショップでの販売、お中元・お歳暮のギフトカタログへの掲載と併せて、羽田空港内の店舗「和蔵場」や、東京・田園調布でのイベントなどのリアルな場での出店も定期的に行っています。
− 地域ブランドを継続するにあたって、今後の課題は何でしょうか。
継続するにはもっと磨き上げが必要ですし、訴求の場も増やさなければいけません。商品の一つひとつは魅力的なので、それを集めて「都の杜・仙台」というブランドとして外に発信していくことが、仙台のPRにつながるのではないかと考えています。
百貨店・藤崎の今らしさ

1819年に創業し、200年以上も歴史を積み重ねてきた藤崎百貨店は、時代ごとの流行やニーズを汲んだコンテンツを多数生み出してきた。東日本大震災、コロナ禍といった未曾有の出来事を背景にした急速な時代の変化のなかで、これからの百貨店・藤崎らしさ、それを伝えるコンテンツをどう生み出していくのだろうか。
− 藤崎らしいコンテンツづくりにおいて感じている課題、それに対して取り組んでいらっしゃることを教えてください。

ものも情報も豊かになった今、我々が何を強みとしていくのか。まだお客様が出会っていない「もの・こと」に藤崎視点の編集やストーリーを掛け合わせて新しいコンテンツを作っていくことが、我々の強みになるだろうということで活動しています。
藤崎百貨店にわざわざ来てくださる理由は、ここでしか味わえないお買い物体験です。今はどこでもものは買えるので、せっかくなら藤崎で買いたいとか、どうせなら藤崎にいるあの人から買いたいって思ってもらえるような関係性をどれだけ作れるか、つまりファンづくりが私たちの強みが発揮できるところなのではないかなと考えています。
リアル店舗では、空間づくりに力を入れています。小さい頃に家族に連れられて来た記憶がある若いお客様が、今、たくさん来てくださるようになっています。そういった方々が特別に用事がなくても来たいと思えるような売り場づくりをと、2023年5月には、本館2階を「リ・プレイス」として大幅リニューアルしました。Z世代・ミレニアル世代を中心としたスタッフによる「もの・こと・ストーリー」の企画や、体験価値を高める空間設計に力を注いでいます。

ここ最近私が意欲的に取り組んでいるのが、地域の様々な分野のクリエイターの方々とコラボレーションした企画です。本館一階のステージで、春にはフローリストによるお花の装飾、秋にはクリエイターがイメージするハロウィンの作品展示など、季節感やテーマ性のある空間づくりを行っています。


また、今年は、年間を通じた藤崎のイメージ発信のために、ストアテーマを決めて社内外に訴求していくことにしました。これまで、会社の発信を従業員で考えたりすることはあまりなかったのですが、今回は若手社員も交えて話し合いました。
今年のストアテーマは「Up To Date」。ファッション用語で“今日的な”を意味します。「Advanced(前進的)」と「Established(確立された)」の間の、ちょうど良いところというニュアンスです。これまでの伝統と、世の中の大きな流れを汲んだうえで、ちょうど良い今日的なところをしっかりとおさえていこうという意志が込められています。
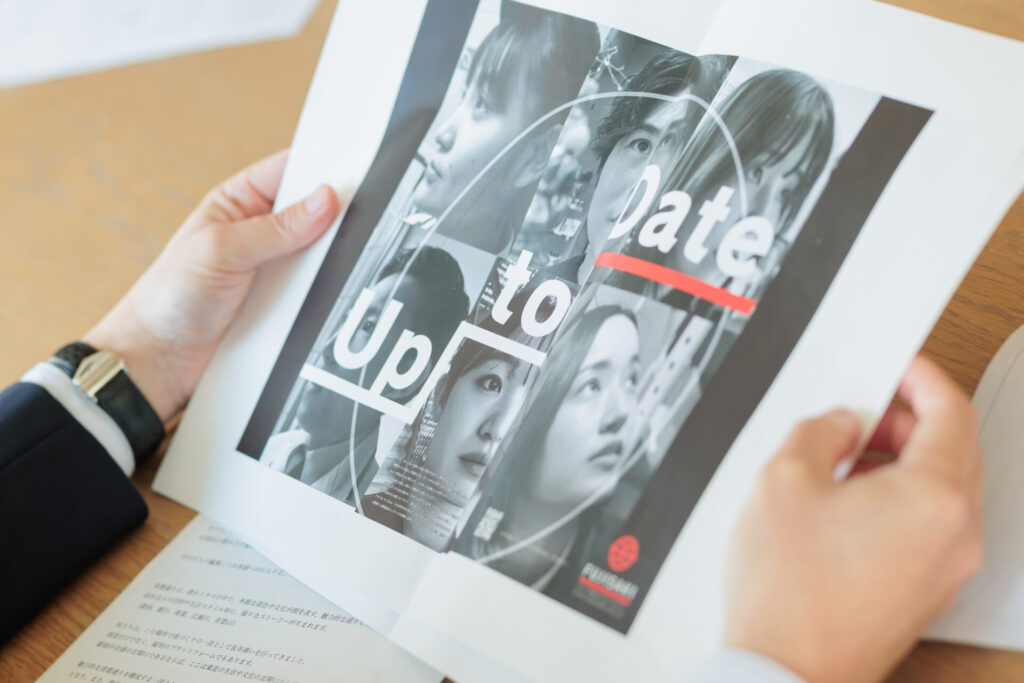
− ストアテーマ「Up To Date」を掲げた館内ポスターを拝見しました。社員の皆さんのお写真が多数掲載されていますね。
そうですね。これが、もの・こと・ひとのプラットフォームである百貨店を伝える、今日的なやり方なのかなと思っています。
ちなみに、ポスターのQRコードを読み込むと観られる動画では、開店前の朝の風景や、閉店後のディスプレイ準備の様子など、昼の百貨店だけではない風景も観てもらおうと思っています。ショーウィンドウのディスプレイも、早いものは一週間のスパンで変えていくので、ディスプレイを作るプロセスや作業している方々の熱量が、お客様に少しでも伝わって共感していただけたら嬉しいです。
− 今までは焦点を当てていなかった百貨店の舞台裏を見せた試みなのですね。 お客様からの反応はいかがですか?
良い反応をいただいています。接客の中でこのポスターの話が出たりするのは嬉しいですね。従業員一人ひとりとお客様との接点を広げるためのツールとして、そして、従業員の皆さんの意識づけとして役に立っていると思います。
青葉通で開く生活と文化の玄関口

− 長い歴史のなかで地域に根ざしてきた藤崎百貨店として、青葉通との未来をどのように描いていらっしゃいますか。
青葉通は、多様な景色や文化の顔があり、訪れる人の生活や目的に合わせて様々なストーリーが生まれています。我々は、この通りの一員として長年商売をしながら成長してきました。仙台駅前が交通の玄関口であるならば、我々は商業の枠を超えた生活と文化の玄関口であるべきではと考えています。しかもそれは、東北一円をターゲットにした玄関口です。
我々が生活と文化の玄関口となり、地域外の人たちが来た時にここに立ち寄ってくれることで、青葉山の素晴らしさを知ったり、秋保方面に回遊したりできるように、文化を繋ぐことを長期ビジョンの一つに描いています。藤崎を中心に街に開かれた取り組みを増やし、豊かさが持続するエリアを作っていけたらと考えています。
− 千葉さんご自身としては、青葉通をどのように見ていらっしゃいますか。そして、今後どのような場所にしていきたいでしょうか。
青葉通は、コラボレーションのしがいがある通りだと思います。仙台駅前から西公園までの長い通りにいくつもの多様な顔があるわけですから、その魅力を作る一員でいたいという思いがあります。
クリエイティブな活動って日々どんどん生まれているじゃないですか。そういうところで仙台って本当に熱いと思うし、東北に拡げるともっと熱いですから、そういった活動と生活者を繋げ、藤崎に来れば東北で一番旬のもの・こと・ひとと出会えるようなお店づくりを続けていきたいと思っています。
目標は、地域のクリエイティブが集まり、暮らしや人生を豊かにするプラットフォームであり、従業員もお客様も、出入りしている事業者さんから清掃の方まで、皆が楽しめる場所を作ること。そのために、これからも日々、小さなコンテンツを積み上げていきます。

常に多様な人が出入りしている百貨店は、どこか街に似ている。あらゆる世代の多様なお客様に向けたコンテンツが集まる藤崎百貨店という場があることは、青葉通の大きな魅力だ。
「店づくりはまちづくりに近いと思っています。青葉通や仙台のブランディングのためにも、街のステータスにあった百貨店のグレードは担保しなければなりませんが、それでも一部の人に向けた閉ざした場所ではなく、開いていく。玄関口なので開いていないと機能しませんから。もっともっと広く開けて、藤崎のファンを増やしていきたい。そうして描いていく未来の青葉通が僕も楽しみです。」
千葉さんは、「皆を巻き込んだり驚かせたりして、共感していただくのが好き」という。独りよがりではなく、街と共に成長し、携わる人々と切磋琢磨していくことに醍醐味を感じている。もちろんそこには、「藤崎さん」と親しみを込めて呼んでくださるお客様への感謝も滲み出ている。
午前10時。開店と共に流れる『好きさ、この街が』のメロディ。歴史を刻んだ、未来に文化を繋ぐ玄関口に立ち、千葉さんは清々しい笑顔で、深々とお見送りのお辞儀をした。

千葉伸也
2005年、株式会社藤崎に入社。販売・バイヤーを経験後、三越伊勢丹へ出向し、都内店舗中心に婦人服の企画・制作などを手がける。藤崎に戻ってからは、中小型店舗の新規出店や本館のフロア改装。産学官のコンテンツ作りや再開発・長期ヴィジョンの策定に携わる。
2023年~コンテンツデザイン部 MD計画を担当
https://www.fujisaki.co.jp(外部WEBサイト)
撮影:佐藤早苗(sanas photo works)
取材・文:奥口文結(FOLK GLOCALWORKS)
場所協力・写真提供:藤崎百貨店
